Contents
DO2. 開発運用サイクル
DevOps領域の2つ目は、開発運用サイクルです。
開発は、コンテンツビジネスで言うところの、コンテンツメイクのことです。
もう一方の運用という言葉は、コンテンツビジネス市場だと、運用代行、Twitter/Insta運用という言葉が聞き馴染みがあると思います。
ITの世界での運用は、”サービスがオンライン上で不具合を起こさずに、稼働させつづける”という意味合いで使われることが多いです。
両者に共通する点は、持続的に稼働させていくことです。
1. 一生売り続けるつもりで開発
メインプロダクトは一生売り続けるものだと思って開発しましょう。
2. 使い方、プロダクトを正しく理解してもらう
僕が情報発信、企画、コンテンツの販売をしてすごく感じたことがあります。
ユーザーさんの多くは、詳細をちゃんと読まないことです。
ちゃんと書いてあるのにも関わらず、「どこですか?」「できません。」「来てません。」とい言われることがありました。
使い方/やり方は、間違いようのないくらい簡潔に、簡単にするのがベストです。
「こうしてあーして、こうやってこうやってください。」みたいに複雑な説明に慣ればなるほど、プロダクトは正しい使い方を理解してもらえなくります。
こんな感じで、消費者の方の中には、本当に簡単なことでも使い方を間違えてプロダクトの価値を体験できずに返ってマイナスに感じてしまうことがあるんですよね。
自分は作った本人なので、当たり前に使い方がわかります。ですがユーザーの方には自身が持っている商品/サービスの常識はありません。
初めて使う人でもわかるように設計し、説明も端的に見つけやすい所に記載しておきましょう。
3. プロダクトを通してユーザーと対話
これは運用観点で重要なことですが、プロダクトは販売して終わりではありません。
販売してユーザーさんが使い始めてからが本当のスタートです。
「ユーザーの声を聞け」とビジネスではよく言われます。
ユーザーの声を聞くことはプロダクトを次に繋げるためだったり、顧客満足度を高めるために必要不可欠な要素と言っていいでしょう。
なので、まずはしっかり使ってくれたユーザーの声を聞くことです。
要望に全部応えればいいわけじゃない
そして、ここで注意が必要なことがあります。ユーザーの声を全部鵜呑みして、プロダクトを改善しようとすること。実はこれ、結構危険なんです。
ユーザーの声をそのまま反映し続けると、プロダクトは多機能ツールになっていきます。
次第に、何んのためのプロダクトなのか迷走しだして、プロダクトのコンセプトが崩壊して魅力がなくなってしまうことがあります。
プロダクトがガチャガチャしててジャラジャラ。
この言葉を聞くだけでも魅力を感じないように、実際のプロダクトも売れなくなるなる危険性があるため、何でもかんでも聞き入れればいいってわけはないということです。
ユーザーの要望の奥にあるもの
ユーザーが気づいていない、ユーザーの表面的な要望の奥にある
本質的な部分に目を向けることが大切です。
4. 本質データを見抜いて施策を重ねる
多くのコンテンツビジネス事業者はこれができません。
そして見込み客の方は無意識に嘘を付きます。
どんな情報を取得し、信じて改善していけばいいのか。
僕はこの点がとても知りたかったので、
もしかしたらあなたも知りたいのではないでしょうか。
僕が特に見ている、顧客の潜在性があわらになる指標を教えますね。
SNSのプロフアクセス数
僕はSNSでは、プロフアクセス数をコア指標としてみています。
インプ、エンゲージメントが大事とかよく言われると思いますが、
僕はこの指標はあとになってから見ていけばいい指標だと思っています。
結局何を目的にしているかというと、「プロダクトの成約」ですよね。
そのためにSNSをやると言っても過言ではないと思います。
そして、プロダクトを買う人が一番見るところはプロフページです。
「この人どんな人なの?信用できるのか?」という疑問を必ず通ります。
そこで「いいな」と思ってプロダクトへ流れるわけなので、
「いかにプロフにアクセスを集めるか」をまず一番に気にしていればいいわけです。
リストIN時のCVR(コンバージョンレート)
プロフをみて「いいな」って思った顧客は、プロフから自身のサービスの入口をくぐって行くわけですね。
そして最終的にリスト(公式ライン/メルマガ)に入ります。
なので、どれだけのプロフアクセスがあって、企画やスクイーズページ(プレゼントを渡すページ)を見て、何件がリストINしたか(CV/コンバージョン)が重要になります。
Twitterであれば、企画ツイートのインプ、エンゲージメントあたりから何割がCVしたか。
そこを分析して、改善してけばCVRを上げて集客効率と集客数を上げていけます。
感想投稿者のその後の動き
あとは、実際に商品を購入してくれた方や、企画に参加してくれた方の
その後の動きに着目すると、プロダクトの修正点などが見えてきます。
「とても勉強になりました。実践します!」
と多くの方は言ってくれるのですが、実は実際追ってみると
全然できてないって事がよくあります。
これは、表面上の理解はできているけれど
実際に行動に落とし込むところまで、
プロダクトが言語化できていない可能性を表しています。
もちろん、商品の開発者の問題ではなく
ユーザー側に原因があって、商品の効果が観測できないこともあります。
なのでそういった場合は、
一人ではなく、複数人の行動割合をみて
プロダクトの改善点を模索していくといいです。

商品を一回開発しておわりではなく、使用しているユーザーをみて
次の改善を運用の中でアップデートして持続化プロダクトにしていきましょう。
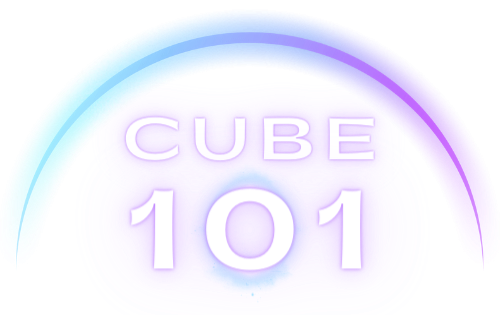

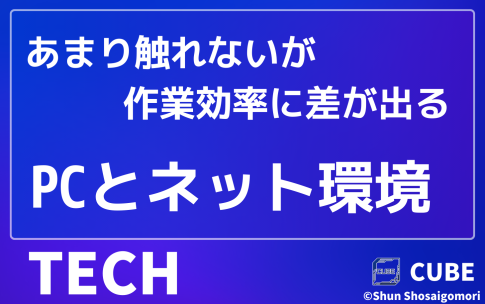




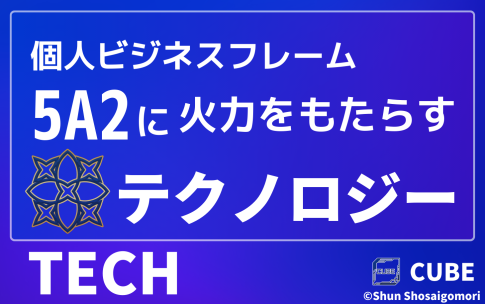

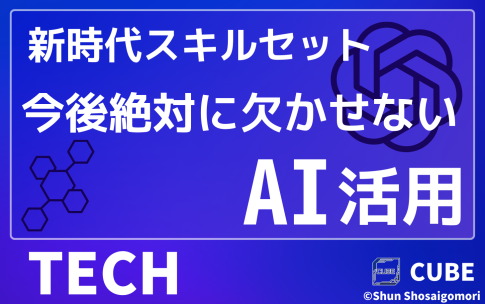

以前、僕がMacBookの裏につけるPCスタンドを買った時の話です。
タイピングしてるときに何度もスタンドが倒れてしまって「何だこの不良品は!」っと思ったことがありました。
しばらくして、僕が反対に付けてしまっている事に気づきました。付け直したら全く倒れることがなくなり、今は「最高のプロダクトだ!」と感じでいます。