DevOps
DevOps(デブオプス)とは
実際のIT系で使われるDevOpsは、開発テストとか難しいカタカタが沢山でできますが、安心してください。
コンテンツビジネスに反映するDevOpsには、専門用語は必要ないので無視で大丈夫です。
重要なのは、なぜを突き詰めた先にある、DevOpsの核を作ってる部分です。
2つの観点
DevOpsとは、上記にもある通り、「Develop:開発」、と「Operations:運用」からなるIT系の造語です。
なぜ僕が、このパット見意味のわからない言葉をコンテンツビジネスに持ってきたかというと、DevOpsが持つ2つの観点が、僕ら取り組んでいるコンテンツビジネスにマッチすると考えたからです。
その2つの観点というのは、「持続」と「開発運用サイクル」のことです。
一言でこの意味を表現してくれるワードってのは全然無いんですよね。
それぞれについてなぜこの観点がいいのかについて説明した上で、それぞれの施策を提示していきますね。
1. 持続
まず持続ですが、これは読んで字のごとくです。
効果が長く続く。つまりビジネスで継続的に売上が上がるという意味です。
僕は過去に、コンテンツビジネスをで、数百部コンテンツが売れる状況も体験しましたが、嬉しい反面、違和感を感じました。
それは、「これ持続しないな。一時の美味しい思いで終わってしまうものだ。売れている今はいいけど、すぐに売れなくなる。」というものです。
作った当初は、どれくらいの期間売れ続けるものなのか、特に対策を練らずともずっと売れてくれるだろうと安易な期待を持ってしまう。これは結構あるあるです。
ですがそうなると、コンテンツを作っても作っても、結局売れなくなってしまうと、永遠に新しいものを生み出し続けなければいけない、悲惨な結末が待っています。
果たしてこれはビジネスと言えのでしょうか?
「自分は、一時の絶頂に便乗する、タピオカ屋みたいなビジネスがしたくてこのビジネスをやっているわけじゃない。」僕はこう思いました。
豊かなビジネスにするには、一時的なものではなく、継続して収益があがってくるように設計する必要があるということです。
2. 開発運用サイクル
開発運用とは、開発サイドがソフトウェアだったりアプリを作って、運用サイドが、サービスがちゃんと回るように監視して維持したり、カスタマーサービスで問い合せに対応していく。
このプロダクトの誕生から走らせることをいいます。
そして、コンテンツビジネスに当てはめると、
開発運用は、プロダクト(コンテンツ/商品サービス)を作る部分が開発、ちゃんと売れ続けるように販売導線を観察し、顧客のフィードバックを抽出したりフォローアップしていくところが運用です。
なぜ、この開発運用というセットの言葉が重要なのかというと、従来のプロダクトは、「開発側は、開発したら後は運用サイドさんよろしく〜。」って感じで、運用サイドに投げる。
「開発→運用」この一方通行の関係で流れで終わるのが主流でした。
そのため一旦、ユーザーの手に届いてしまうと大幅な修正ができないために、プロダクト1リリース→プロダクト1終了→プロダクト2リリース…プロダクト3,4…みたいな感じで、途切れてアップデートされる。プロダクトも断続的リリースが主流だったわけです。
しかしながら、昨今のオンラインプロダクトは更新し、継続することができるようになりました。
「パッケージはそのままでアップデートできるよね」ってことです。
従来:開発→運用(プロダクト1、プロダクト2
現代:開発∞運用(プロダクト:Ver1.0→Ver2.0
ちょっと、難しかったかも知れませんが、一個を磨き続けるか、一個目の反省いかして2個目作るかの違いです。
デジタル化が進んだ今、プロダクトは、オンライン上におくことができるため、顧客の手に渡った後であってもすぐに改良できる用になりました。
1個を磨き続けて価値を継続的に届けることができるということです。
その方がプロダクトの持続に適しています。

ゲームだと、APEXとかフォートナイト、ドラクエⅩ、FF14みたいなプロダクトは持続しています。
ナンバリング系のプロダクトのいい例は、ウイニングイレブンとかスポーツ系のゲームですかね。時期が過ぎたら一瞬で価格が暴落します。
今のコンテンツビジネスの主流は後者みたいな感じで、ピーク時にバン売りきるスタイルがメジャーなので持続しないんですよね。
持続と開発運用の2観点とビジネス
この2つの観点から個人のコンテンツビジネスの成果につなげる話をこれからしてきます。
非常に重要ですし、語れる人が少ない内容です。
ぜひ最後まで読んで、頭に叩き込んみ自分の事業に反映してみてください。
それでは、持続、開発運用の2観点からコンテンツビジネスアプローチしていきます。
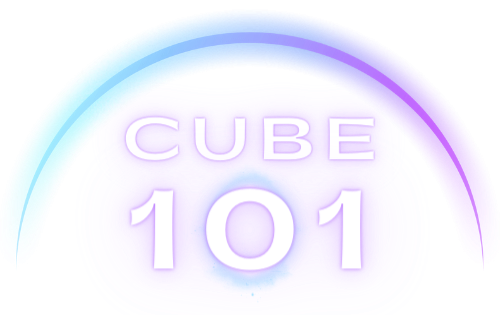

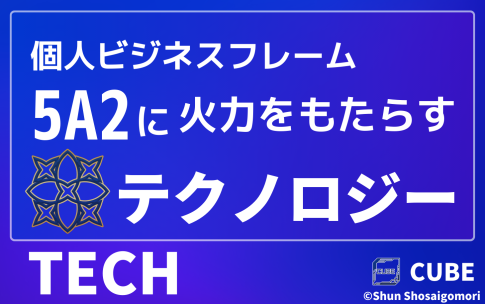

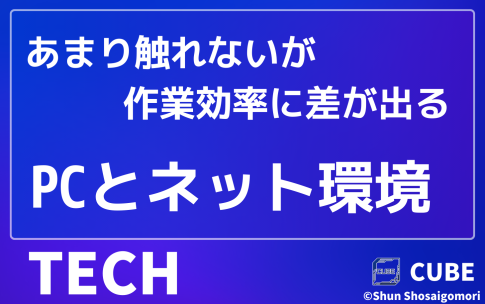

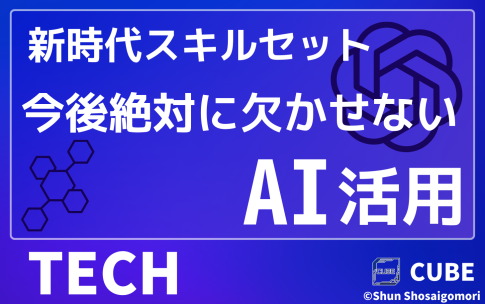




モンスタハンター1→モンハン2→モンハン2Gみたいにゲームで考えるとわかりやすいでしょうか。